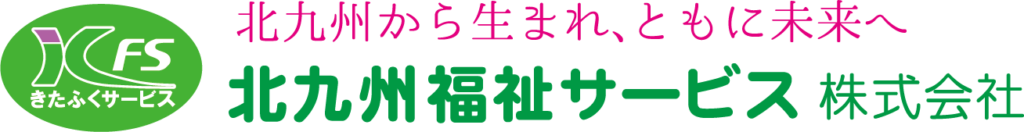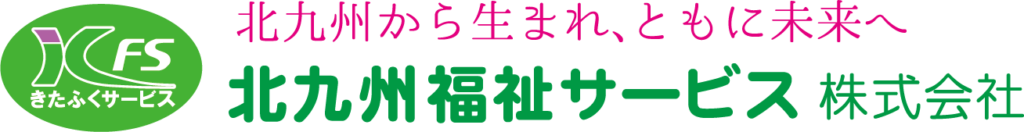1.虐待防止に関する基本的考え方
きたふくでは、お客様の人権を尊重し、下記の虐待の定義の内容および関連する不適切なケアを一切行わないこととする。また、虐待の発生の防止に努めるとともに、早期発見、早期対応、再発防止について、すべての社員がこれらを認識し、本指針を遵守して、高齢者・障がい者福祉の増進に努めるものとする。
【虐待の定義】
虐待とは、社員等からお客様に対する次のいずれかに該当する行為をいう。
(1)身体的虐待
お客様の身体に外傷を生じ、もしくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なくお客様の身体を拘束すること。
(2)性的虐待
お客様にわいせつな行為をすること、またはお客様をしてわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待
お客様に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)介護放棄(ネグレクト)
お客様を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前三項に掲げる行為と同様の行為の放置、お客様を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(5)経済的虐待
お客様の財産を不当に処分すること、お客様から不当に財産上の利益を得ること。
2.虐待防止管理体制
(1)虐待防止委員会
①組織
各事業部の責任者が参加する全社虐待防止委員会と各事業所が運営する各事業所虐待防止委員会を設置する。
②委員の選出
委員の構成は別表1のとおりとする。各事業所虐待防止委員会は責任者および担当を含めて2名以上とする。
また、委員および担当には、必要がある場合にはお客様やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等を加えることができる。
③委員会の開催
委員会の開催を次のとおりとする。
ア 全社虐待防止委員会は、年1回定期開催する(12月)。
イ 各事業所虐待防止委員会は、年1回定期開催する(6月)
ウ その他虐待事例が発生した場合など委員会の開催の必要な場合は、委員長および責任者が招集し開催する。
④委員会の責務
全社虐待防止委員会および各事業所虐待防止委員会の責務は以下のとおり。
【全社虐待防止委員会】
ア 虐待防止に関する指針の作成と改訂
イ 委員会の開催、研修等の様式の整備
ウ 次年度の共通研修の計画・確認
エ 各事業所の研修・委員会の実施の促し
オ その他(情報共有など)
【各事業所虐待防止委員会】
ア 虐待発生時の対応と報告および記録作成
イ 虐待防止に関する研修の実施・確認
(2)研修の実施
全社虐待防止委員会は、虐待防止に関する研修プログラムを年度単位で作成し、全社および各事業部の研修の実施状況を確認する。また、全社における定期的な研修を実施する(年1回以上)とともに新規採用時には本社および各事業部で実施する新人教育にて、必ず虐待防止に関する研修を実施する。
各事業所では、各事業部で実施する年間研修計画にて虐待防止に係る研修を実施する(年1回以上・GHは年2回以上)。各事業所では研修の実施に関する記録を作成、保管する。
(3)記録の保管
委員会の開催および研修、訓練について、各事業所単位で記録を作成し、保管する。
3.虐待が発生した場合の対応方法について
虐待事案が発生した場合、各事業所の虐待防止責任者は各事業所虐待防止委員会を開催し、全社虐待防止委員会の委員・発生部署の担当者、所轄する部長等とともに虐待事案の検証を行い、かつ再発防止策の検討を行う。
また、各事業所虐待防止委員会は所定の報告書にて会社へ報告を行い、提出された事例は会社で集計し、他社員および他部署へ周知する。
【対応手順】
(1)加害者が社員以外の場合
責任者(所長)へ報告
本人または社員等から相談を受けた社員は、速やかに現場責任者(所長等)へ報告し、所長は上長(次長・部長)へ報告する。

CM・相談支援員へ相談
担当のケアマジャーや相談支援員がいる場合は実情を伝え、対応を協議する。

行政へ通報
CM・相談支援員と相談の上、虐待と疑われる事例については、地域包括支援センター、北九州市障がい者虐待防止センターおよびこども総合センターへ通報する。
その後は行政の要請へ対応する。

社内報告書提出
現場責任者は、「虐待事例報告書」に必要事項を記入の上、本社へ提出する。
(2)加害者が社員の場合
上長へ報告
現場責任者は、「虐待事例報告書」に必要事項を記入の上、本社へ提出する。

実態調査
報告された上長は、虐待の実態・経緯・背景等を関係者からヒヤリングを行い把握する。虐待と認められないケースは個別に対応する。

市へ報告
虐待とみなされる場合は、市担当部局へ報告する。
介護:各区地域包括支援センターおよび本庁
障害:北九州市障がい者虐待防止センター(093-861-3111)
児童:こども総合センター(093-881-4556)

再発防止策策定
現場責任者は上長と相談の上、再発防止策を策定する。

社内報告書提出
市の報告
現場責任者は、「虐待事例報告書」に必要事項を記入の上、本社へ提出すとともに、市へ再発防止策を報告する。

加害者への懲罰
虐待を行った社員に対しては、就業規則に基づき適切な処分を行うとともに、再発防止のための再教育を行う。
5.成年後見制度の利用支援に関する事項
事業所は、家族がいないまたは家族の支援が著しく乏しいお客様の権利擁護が図られるよう、親族および地域包括支援センター等と連携し、成年後見制度が利用できるよう支援するものとする。
6.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
各事業所は、虐待に係る苦情が生じた場合、誠意をもって対応するとともに、市町村、国民健康保険団体連合会においても苦情を受け付けている旨を家族等に伝えるものとする。
7.お客様に対する当該指針の閲覧に関する事項
本指針は、サービス利用者、入所者(お客様)およびそのご家族がいつでも閲覧できるよう、弊社のホームページに掲載し、常時閲覧可能な状態とします。
また、お客様およびそのご家族からの希望があれば、指針の内容をご説明します。
8.その他虐待の防止の推進のために必要な事項
2.(2)に定める研修のほか、関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、お客様等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう研鑽に努める。
【別表1】
■全社虐待防止委員会名簿
| 役職 | |
| 委 員 長 | 総務部 部長 |
| 副委員長 | 生活提案事業部 部長 |
| 委 員 | ヘルパー事業部 統括次長 |
| 〃 | 施設事業部 次長 |
| 〃 | 訪問看護ステーション 所長 |
| 第三者委員 | 必要に応じて招集 |
■各事業所虐待防止委員会名簿
| 事業所 | 責任者 | 担当 |
| ケアプランサービスセンター門司 | 岩田 | 松尾 |
| ケアプランサービスセンター小倉北 | 宮崎 | 原 |
| ケアプランサービスセンター小倉南 | 野田 | 長岡 |
| ケアプランサービスセンター若松 | 崎長 | 平岩 |
| ケアプランサービスセンター八幡東 | 池田 | 黒田 |
| ケアプランサービスセンター八幡西 | 太田 | 木附 |
| ケアプランサービスセンター戸畑 | 宇野 | 浅尾 |
| きたふくヘルパーセンター門司 | 武藤 | 茶島 |
| きたふくヘルパーセンター小倉北 | 上野 | 金岡 |
| きたふくヘルパーセンター小倉南 | 藤原 | 福吉 |
| きたふくヘルパーセンター八幡東 | 竹内 | 徳弘 |
| きたふくヘルパーセンター八幡西 | 石本 | 白石 |
| きたふくヘルパーセンター戸畑 | 田原 | 藤岡 |
| きたふくデイサービスセンター「自悠茶論」皿倉 | 小林 | 木多良 |
| きたふくデイサービスセンター「自悠茶論」大里 | 安部 | 三浦 |
| きたふくデイサービスセンター「自悠茶論」志徳 | 佐藤 | 馬場 |
| きたふくデイサービスセンター「自悠茶論」幸神 | 松下 | 木原 |
| きたふくグループホーム「自悠の郷」幸神 | 原 | 小野 |
| きたふく小規模多機能ホーム「自悠の庵」幸神 | 池田 | 宮崎 |
| 北九州福祉サービス株式会社 福祉用具貸与 | 内田 | 青木 |
| きたふく訪問看護ステーション | 石丸 | 山本 |
| きたふく相談支援センター | 三ツ広 | 金子 |
<更新履歴>
| 更新日 | 更新内容 |
| 2022年1月18日 | 作成 |
| 2024年4月24日 | 2.虐待防止委員会その他の各事業所内の組織に関する事項(2)を追加 |
| 2024年9月20日 | 虐待防止委員会運用規程を2.虐待防止管理体制 (1)虐待防止委員会に組み込み、虐待防止委員会運営規程は廃止。 |
| 2024年12月12日 | 全社虐待防止委員会 ウ・オ 追加 各事業所虐待防止委員会 イ 確認を追加 |
| 2025年4月21日 | 7.お客様に対する当該指針の閲覧に関する事項を追加 |
◆法令および規程に基づき、委員会が定期的に実施する具体的事項
1.組織
各事業部の責任者が参加する全社虐待防止委員会と各事業所が運営する各事業所虐待防止委員会を設置する。各事業所の責任者および担当者は最低2名以上。
2.委員会の開催
(1)定期開催
①全社虐待防止委員会
開催日時:毎年12月・年1回
検討内容:全社情報連絡会で実施(毎年6月)する研修の決定
当該年度の研修実施結果と次年度の研修計画の取りまとめ
開催記録:議事録を作成し、全社虐待防止委員会にて保管する。
②各事業所虐待防止委員会
開催日時:毎年6月・年1回
検討内容:・・・・
開催記録:実施記録を作成し、各事業所にて保管する。
- 不定期開催
虐待事案が発生した場合は、各事業所の虐待防止責任者は各事業所虐待防止委員会を開催し、発生部署所属の全社虐待防止委員会の委員および発生部署担当者、所轄する部長等とともに虐待事案の検証を行い、かつ再発防止策の検討を行う。
3.研修の実施
①全社研修
開催日時:毎年6月・年1回
実 施:毎年12月に開催する全社虐待防止委員会にて内容を決定。
全社情報連絡会で実施した研修は、各事業所にて伝達研修を行い、各事業所にて開催記録を作成、保存する。
②各事業所研修
各事業部にて年間計画を策定、実施。各事業所にて開催記録を作成、保存する。
4.虐待事例の報告
各事業所より「虐待事例報告書」を本社へ提出。
報告書は事故報告と同様、各部門から部長、社長へ報告を行う(総務部取りまとめ)
報告書は提出された都度、委員長より全管理職へメールにて配信する。
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日)
(厚生省令第三十七号)
(虐待の防止)
第三十七条の二 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三厚労令九・追加)